「5度と6度の予備練習」, 『バスティン ピアノ レベル2』, p. 12.
新しい音ということで、真ん中のド(C4)より一つ隣の低いシ(B3)が登場。
うん。これは知ってたw『グルリット初歩者の~』の割りと最初のほうで出てきたんで
5度と6度の予備練習
え?まだ5度と6度やるの?w もうけっこうやったよ?
と思ったら
はじめに,楽譜どおりに ひきましょう。つぎに、FとGの調に移調(ちがう調 でひくこと)しましょう。
だそうです。道理で、いきなり簡単そうな譜面になってるわけだw
あと、同じ5度と6度でも、今度はソ(G4)から低い方に5度(ド;C4)と6度(シ;B3)ということみたいです。
なるほど~。低い方にも数える練習と、移調練習という意図かー。
って、説明こんだけ??(;・∀・)
まあ、ヘ長調とト長調は前巻からこれまでさんざんやってきたけどさ~
曲の中でも「移調」って書いてなくても、「これ移調というか、転調というか、だな」っていうのがいっぱいあったけどさ~
いきなり「さぁ、やってみろ!」ってかいぃ(; ・`д・´)
こりゃ、移動ドの出番かね…?
ええと、、、
ヘ長調の場合、ファがドだから、ドがソで、、ミがシで、、、
………
うぎゃーーーーっ!ややこしい!!!ヽ(`Д´#)ノ
まあ鍵盤を見ながら、相対音感な耳で聴きながら弾いていったほうが早いなこりゃw
頭ン中で考えるとかえって難しくなる。。。
でもなあ、、、一応、音度を数える練習もしなきゃなのかな?
ええと、、、
- ヘ長調の場合、ファが1度で、5度はドで、ファから2度低い音はミで・・・
- ト長調の場合、ソが1度で、5度は、レで、ソから2度低い音は・・・えっと…ファの♯じゃないか!
いや、まて、これは第5音を基準にして、低い方に度数数えなきゃなのか?やっぱ
- ヘ長調の場合、第5音はドで、そこから5度下はファで、6度下は、ミ
- ト長調の場合、第5音はレで、そこから5度下はソで、6度下は、ファ♯!
うー…やっぱり言葉で書くとややこしい!
ああーも~、はじめての「移調練習」なんだし譜例あってもいいじゃんよ~(´・ω・`)
というわけで、つくったった!
『バスティン』シリーズの表記に従って、「メジャー」じゃなくて、ちゃんと「メージャー」にしましたよっとw
もし、これから練習するって方で、自分みたいに「いいーーーっヾ(*`Д´*)ノ"」ってなった方がいらっしゃったら、どうぞw↓
●ヘ長調ヴァージョン!
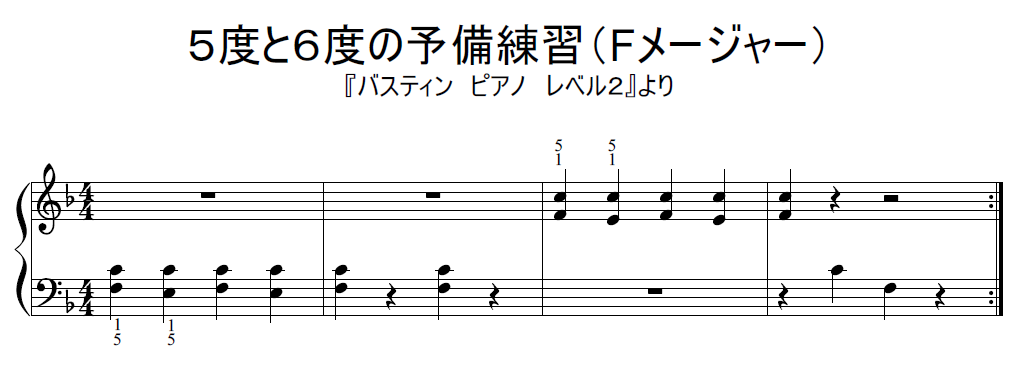 |
| ※画像クリックで拡大表示します。 |
●ト長調ヴァージョン!
 |
| 調号が効くファに色付けてみました。 ※同じく画像クリックで(以下略) |
てか、運指はこのままでいいのかな?
個人的にはト長調ヴァージョンの左手ファ♯は5指よりも4指の方が弾きやすい気がするんだけど、、、でも6度だしなあ…やっぱ5指なんだろうなあ。。。















